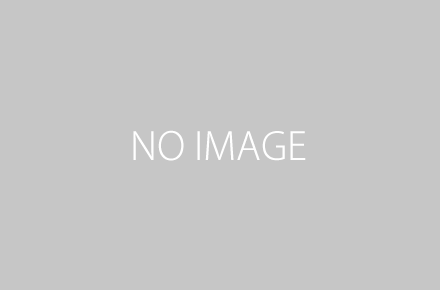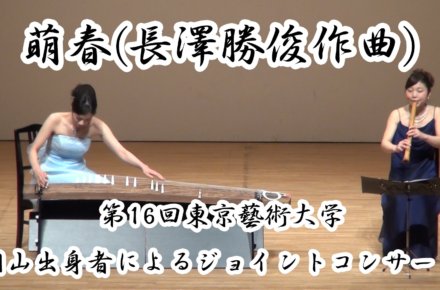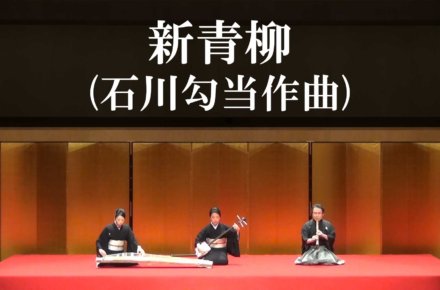萩の露(幾山検校作曲)
福田恭子第1回博士リサイタルより
(箏:岡村慎太郎/三絃:福田恭子)
解説
幾山検校作曲
川瀬霞紅園作詞
この曲の秋の情景に寄せた歌詞には、始めに秋の七草、松虫に砧、月に雁と秋の景物を並べているが、秋の情緒を添える一つ一つの言葉が、この曲の内容を一層深くしている。
女性が一度身を任せた男性に見放されながらも、まだ恋慕ってやまず、せめてもの慰めに手紙でも送ろうかと、男性を尾花に、女性を萩に、その萩に宿る露を涙にたとえた所から《萩の露》という曲名となった。
前歌の後に普通の「合」よりは少し長い「合の手」が入れられて、女性のはかない心情を主題とする「砧(きぬた)」を描写している。
器楽曲としての「砧物」ではないが、「八重衣」などとともに、砧の描写を含む広義の「砧物」の一つと考えられる。
作曲年次は明らかではないが、京風手事物としては、ほぼ幕末最後の方の作品と考えられ、作曲者幾山検校自身が、五十歳前後に相当し、作曲としては壮年期で最も円熟していた時代の作曲であったと思われる。
歌詞
何時(いつ)しかも、招く尾花に袖触れそめて、我から濡れし、露の萩。
今さら人は恨みねど、葛の葉風のそよとだに、おとずれ絶えて松虫の、ひとり音(ね)に鳴くわびしさを、夜半に砧の打ち添えて、いとど思いを重ねよと、月にや声は冴えぬらん。
いざさらば、空行く雁に言問わん。
恋しき方に玉章(たまずさ)を、送る便(よすが)の有りや無しやと。
通釈
いつの頃であっただろうか。
尾花に招かれたように、われから求めて身を任せ、袖触れ合い、契りをかわしたが、今は涙の思い出である。
今さら去った人を恨むわけではないが、まるで葛の葉が風に吹かれて裏返り、そよという風の音さえ絶えてしまったように、秋の空と男心は、待ちかねているこちらの心を知ってか知らずか、ちっとも便りをくれない。
松虫が誰かを待つのか独り鳴いているわびしさを、遠く聞こえる夜半の砧の音が響き、さらに想いを募らせる。
わびしいときは思う限りに思うてみよと、無情にも秋の月夜に砧の音が冴え渡って聞こえてくるようだ。
雁の鳴き声を聞いて、さあそれならば、と空を飛ぶ雁に呼びかけ尋ねたいことがある。
せめてもの慰めにかつて身を任せた恋しい方に手紙を送りたいと思うが、その手紙を何とか届ける方法はないものであろうかと。
箏曲演奏家 福田恭子