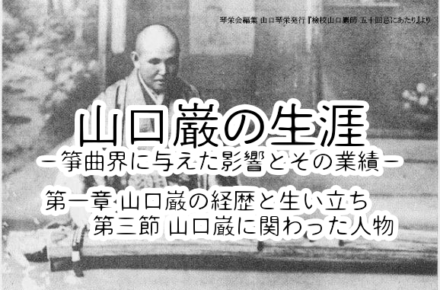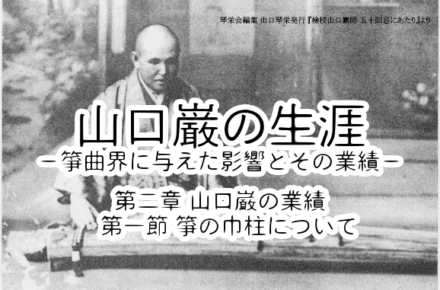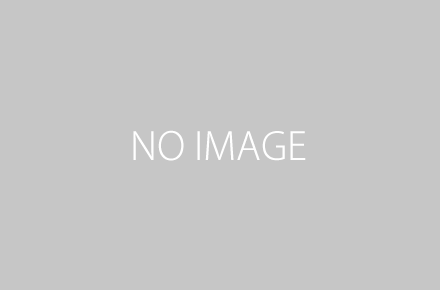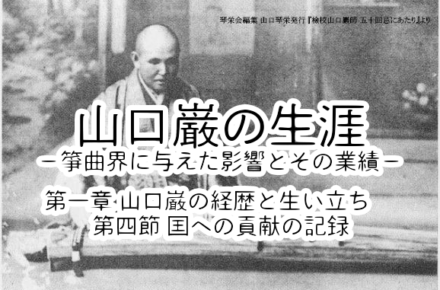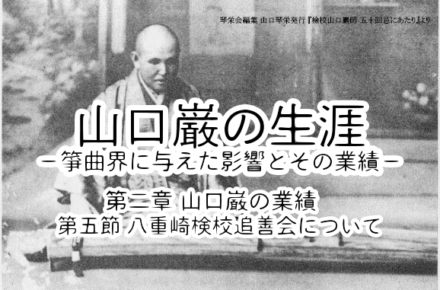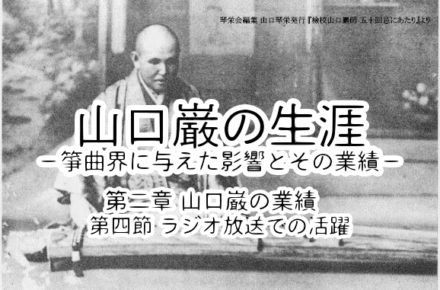修士論文「幾山検校の生涯―《萩の露》を中心に―」要旨
本論文は幾山(栄福)検校の生い立ちを調査し、その作品のなかで地歌箏曲の名曲とされている《萩の露》を中心に考察を行ったものである。
幾山検校は、幕末から明治にかけての大きな変革の時代に生き、京風手事物の最後の作曲者といわれている。
幾山について残されている文献や資料は極めて少ないが、ただ芸一筋に生涯を捧げたといわれ、本論文では、幾山がどのような人生を辿ってきたのかということを明らかにするための研究を行った。
第一章
本章では、幾山から実際に手ほどきを受けた人物が、その思い出を語る文献から、幾山についての人物像や経歴を辿った。
明治13年に京都盲唖院(現在は京都府立盲学校)の顧問に任命されていたということから、幾山は、演奏や作曲活動だけでなく、音楽教育にも従事していたことがわかった。
作曲家として有名である幾山検校であるが、京都盲唖院での活動自体はあまり知らいない。盲唖院での活動を調査するため、実際に京都府盲学校の資料室に赴き、裏付けとなる史料や文献から調査を行うことにより、「幾山(栄福)検校」の所在を証明し、その事実を明らかにすることができた。
幾山検校の楽曲については、現存している曲は少ないものの、その作曲数は約30曲である。このなかでも、伝承されているものはわずかであり、現在楽譜の現存していない曲に関して楽曲の詳細は不明である。
しかしながら、幾山の作品のほとんどの歌詞は、箏曲の地歌歌本に残されており、それら歌詞を歌本から翻刻し、歌詞の内容と曲種について調査することができた。この調査によって、幾山の作品の特色を歌詞の内容からとらえることができ、各楽曲の作曲年次についても、歌本の刊行年と楽曲の種類から、幾山の壮年期から晩年までの作曲順をおおよそ推測することができた。
第二章
本章では地歌の合奏形式である〈打ち合わせ〉を考察し、幾山検校が〈打ち合わせ〉曲として作曲した《打盤》と《横槌》について解説した。
また、幾山の作品のなかでは、現在も箏曲界で多く親しまれている、《萩の露》がもっとも代表的な作品である。この曲は、江戸時代から明治時代へと時代の移り変わる中で、古典的形式をとる京風手事物で作曲され、幾山は、江戸時代最後の京風手事物の作曲者ともいわれている。
本研究では、幾山の作曲の特徴を捉えるために、《萩の露》の分析を行った。
《萩の露》の歌詞からみた分析では、それぞれの歌詞に詠まれている秋の風物や、その情景を表現した手法や音型を抽出し、歌詞との関連性を検証した。
手事部分からみた分析では、それぞれの節や旋律を部分的に細かく区切り、箏・三絃の合奏の成り立ちを分析した。さらに、《萩の露》で用いられている手法や音型、また部分ごとの箏・三絃の合奏を構成ごとに分類し、それぞれの頻度を割り出したことで、楽曲の特徴や性質をとらえることができた。
地歌箏曲の作曲の成り立ちは、先に三絃が作曲され、後に三絃の作曲者とは異なる作曲家によって、箏が手付される楽曲がほとんどである。これに対し幾山は、ほとんどの楽曲を、箏・三絃どちらも自ら手付したことがひとつの業績でもある。
《萩の露》の分析では、箏・三絃の合奏は複雑に絡み、巧妙な手付がされ、歌詞の内容を感じさせるよう、細部まで手の込んでいる作曲がされていることがわかった。
まとめ
芸の道一筋に生涯を捧げてきた幾山は、多くの作曲を残し、京都での演奏活動を中心に、芸道の存続のために貢献し、京都盲唖院の財政復興に尽力し、京都の女学校の絃歌の指導をはじめ、盲唖院の音曲指導に献身した人物であった。
また、幾山は三絃の演奏家として活躍し、幾山自身の演奏が、三絃は鐘鈴のような美しい音色で、節を巧みに生かすことができた人物だったといわれている。このことは、幾山の作品の多くが三絃曲であった所以であると考えられる。
本研究により、幾山が礼儀正しく謹厳な人柄であったといわれ、芸に対する誠実な態度であったことが、その作品に繋がり、作曲がいかに精密で、奥深い感情が曲に込められているかということが明らかとなった。
幾山は生涯独身とされていたため、子孫は残っていないが、津田道子氏の『京都の響き 柳川三味線』によると「家系は今も続いている」とある。今後、今も続いているかもしれない家系に関わる方への調査が可能ならば、幾山の人物像を知るひとつの手がかりとなるともいえるだろう。
また、幾山の残した作品や、幾山の活動を示す文献や記録を発掘し、さらに幾山の生涯を明らかにすることが今後の目標である。そして、幾山検校という人物の生涯や人物像があまり知られていなかったなかで、本研究を参考に、幾山の作品の分析や演奏に役立てられることを願う。
《萩の露》について
この曲は明治初期の作品とされ、幾山検校自身が五十歳前後に相当し、技術や感性などが最も円熟期であったといわれている頃の作曲である。《萩の露》は幾山の作曲の芸術性が集大成となって現れている曲といえるだろう。
幕末から明治初期にかけて時代の変遷とともに、箏曲にも新しい風潮がみられるようになったが、古典的である京風手事物の形式で作曲されている。その楽曲構造は、〔前歌〕・〔合の手〕・〔手事(マクラ)(本手事)(中チラシ)(本チラシ)〕・〔後歌〕で構成されている。
作詞者は川瀬霞紅園である。歌詞は、秋の景物になぞらえて女性の恋情が情緒的にうたわれている。
この秋の情景に寄せた歌詞には、始めに秋の七草、松虫に砧、月に雁と秋の景物を並べているが、秋の情緒を添える一つ一つの言葉が、この曲の内容を一層深くしているといえる。
男性を尾花に、女性を萩にたとえて、その萩に宿る露を涙にたとえた所から《萩の露》を曲名としている。男性からの便りもなく、その姿も見せなくなったことで、秋の月夜に辛くわびしい思いを募らせている。女性が一度身をまかせた男性に見放されながらも、まだ恋い慕ってやまず、せめてもの慰めに手紙でも送ることができないだろうかと雁に問うている。この曲は二度と会えないという嘆く感傷的な意味もあり、一説には、追善曲ともされている。
[歌詞]
何時(いつ)しかも、招く尾花に袖触れそめて、我から濡れし、露の萩、今さら人は恨みねど、葛の葉風のそよとだに、おとずれ絶えて松虫の、ひとり音(ね)に鳴くわびしさを、夜半に砧の打ち添えて(合の手)いとど思いを重ねよと、月にや声は冴えぬらん(手事)いざさらば、空行く雁に言問わん、恋しき方に玉章(たまずさ)を、送る便(よすが)の有りや無しやと
《萩の露》は歌詞の内容に沿って、さまざまな奏法や特徴的な音型が用いられている。秋の風情を表す言葉になぞらえて、女性が男性を慕うわびしい心情と重ねられ、歌詞の内容に基づいた手法や旋律が手付されている。
この曲を象徴する手法としては、【裏連】が最も用いられ、《萩の露》の「涙」を連想させる部分に多くみられる。特に曲の終わりの〔後歌〕のなかに【裏連】が多く用いられているのは、その短い歌の間に一度にして、「露」という言葉に込められた女性の深い感情を想起させ、曲全体が統一性をもって終末を迎えられるように工夫されている。
また秋の風物として、「虫の音」や「砧」の音型が箏・三絃ともによく現れる。〔前歌後の合の手〕は最も顕著に現れており、女性の辛さを、秋の物悲しい情緒にのせて表現している印象的な部分である。そして、「砧」を表す音型が全体を通して多くみられたことは、《萩の露》が「砧」を象徴している楽曲であるともいえる。
箏曲演奏家 福田恭子